
普段から口にする「塩」を気にしたことありますか??
「塩は体に悪い」「減塩しないと高血圧になる」とよく聞くけれど、本当にそうなの?精製塩と天然塩では健康への影響が違うの?
こうした疑問は多くの人が抱くテーマです。実際、塩分過多は高血圧や心血管リスクと関連すると言われ、WHOや日本でも減塩政策として「1日6g未満」が推奨されています。しかしその根拠や、精製塩と天然塩の違いが健康にどう関わるかについては、科学的に明確に証明されたわけではありません。
本記事では、
ナトリウム摂取と高血圧の科学的根拠、
精製塩と天然塩の成分の違い、
減塩政策の背景や胃がん・ピロリ菌との関係、
そして日常生活での塩や調味料の選び方まで、
分かっていることと分からないことを整理しながら、現代人がどう意識して選択すべきかを考えていきます。

今回は人間にとって欠かすことのできない「塩」の話ですね
塩分と高血圧に関する科学的知見

- ナトリウム摂取量が多いと血圧や心血管リスクが上がる傾向が示されている
- 個人差(塩感受性)があり、すべての人に一律に当てはまるわけではない
- 研究デザインや解析方法で結論が揺れる研究も存在する

塩ではなくて「ナトリウム」の話なんですね・・・。
解説:
INTERSALTやDASH-Sodium試験など、24時間尿ナトリウムを用いた大規模研究では、ナトリウム摂取量と血圧・心血管疾患リスクの関連が示されています。ただし効果の大きさや閾値には個人差があり、塩感受性が低い人もいます。また、極端に低ナトリウムの場合のリスクを指摘する研究もあり、単純な直線的因果では説明しきれません。「塩=悪」と断じるのではなく、科学的に分かっていることと不確実性を区別する必要があります。
精製塩と天然塩の科学的比較

- 精製塩はNaClが99%以上で、微量ミネラルをほぼ含まない
- 天然塩はK・Mg・Caをわずかに含むが量はごく微量
- 天然塩と精製塩の長期健康影響を直接比較した大規模研究は存在しない

塩と健康を論じる際に、塩の質、何由来の塩か?は論じられることはありません。
解説:
天然塩と精製塩は製法や成分が異なりますが、KやMgなどの含有量はNaと比べると桁違いに少ないため、これら微量ミネラルが血圧や健康にどの程度影響するかは科学的に明らかではありません。長期・大規模な比較試験は研究デザイン上難しく、現時点で健康影響に差があると断定するエビデンスはありません。この点は「分かっていない領域」として正直に記述することが重要です。
政策としての減塩目標(6g未満)の背景

- WHOはナトリウム換算2g(食塩換算5g)未満を推奨
- 日本は現状を踏まえ、男性7.5g、女性6.5g未満を目標とする
- 加工食品・外食由来の高ナトリウム摂取を減らす政策的意図が強い

外食や加工食品の摂取量を見直すことが大事なんですね。
解説:
日本の減塩目標は、WHO推奨値に近づけるための現実的なステップです。塩分摂取源の多くが加工食品や外食に由来するため、政策としてこれらを減らす意図があります。歴史的に日本では塩分摂取量が多く、脳卒中や胃がんが多発していました。減塩政策により脳卒中死亡は大幅に減少しましたが、胃がんについては塩分よりもピロリ菌感染と除菌の寄与が大きく、減塩は補助的な要素と考えられます。
「偽物」論と調味料の選択

- 精製塩や速醸調味料は安全基準を満たした合法食品
- 伝統製法の調味料は旨味や香りの奥行きがあり、文化的価値が高い
- 「偽物か本物か」は法律的な区別ではなく、製法や価値観に基づく選択の問題
解説:
現代の調味料や食品は、安価・大量生産のために短期製造や簡略化が行われています。例として、新式醤油(アミノ酸液・カラメル添加)、みりん風調味料、速醸酢などが挙げられます。これらは法的にも安全性評価的にも正規品ですが、昔ながらの発酵・熟成による旨味や文化的価値とは異なります。「偽物」という言葉は科学的な分類ではなく、生活哲学や価値観に基づいた表現として捉えるのが適切です。

自分は、塩、味噌、醤油などの調味料はできるだけ「自然由来」であることを優先しています。
曖昧さと個人の選択

- 科学ですべて白黒つけることは難しい分野がある
- 分からないからこそ、自分の価値観で選ぶ余地がある
- 過剰な神経質や我慢は逆効果、バランスと妥協も大切

これがいわゆる「専門家でも意見は分かれる」ということですね。
解説:
精製塩と天然塩の健康影響のように、証拠が不十分なテーマは多く存在します。だからこそ、「証拠がない=意味がない」ではなく、「分からないからこそ自然な製法を選ぶ」「文化や味わいを重視する」といった選択があり得ます。過剰に恐れる必要はなく、便利さや価格、健康や文化への思い、そのバランスを考えて各自が納得する選択をすることが大切です。小さな意識の積み重ねが、予防や生活の豊かさにつながります。

皆さんも、情報を整理して自身の価値観や生活スタイルにあった選択をしてください。


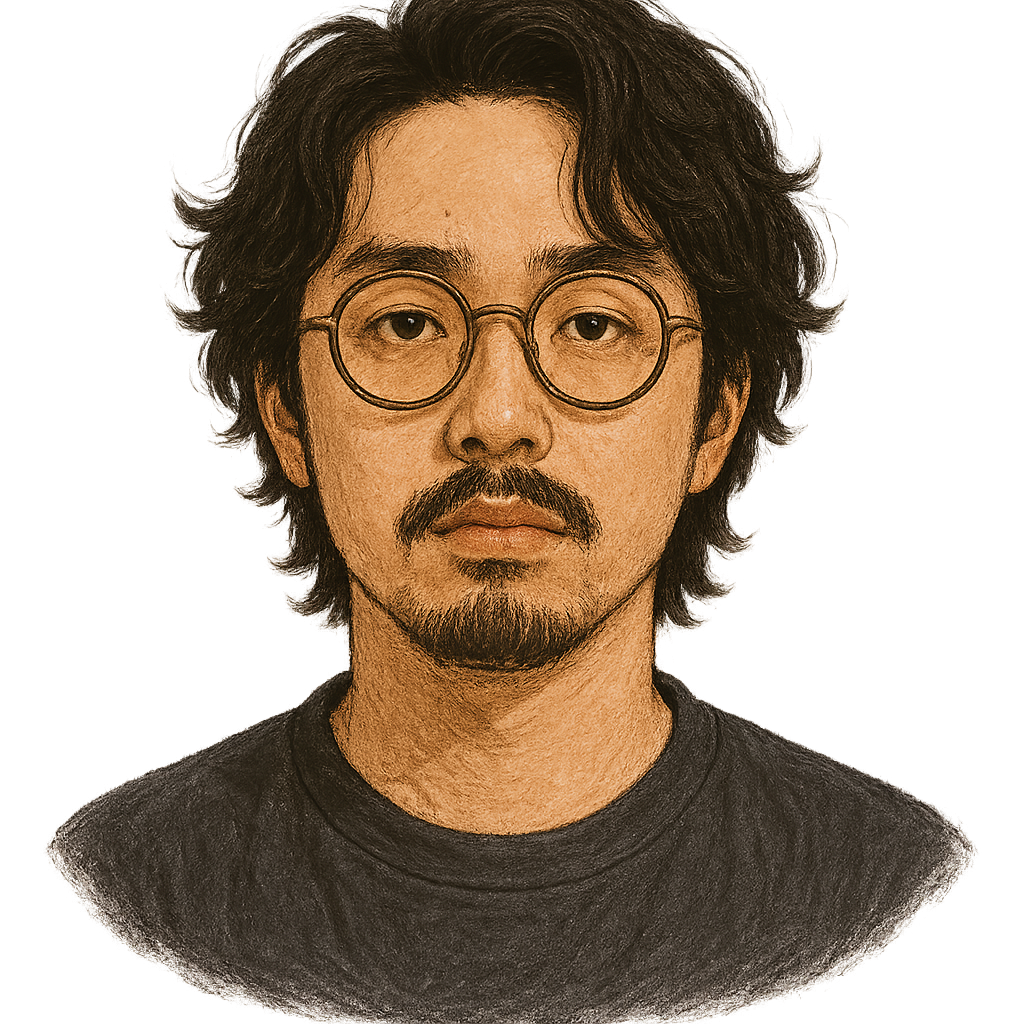

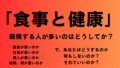
コメント