小麦に関する噂を科学的な視点から考えてきましたが、「専門家の意見は一致しない」ので結論を出すことはできません。結局のところは専門家に頼るのではなく自身で判断していく世界線です。
とはいえ、セリアック病や小麦アレルギーでない限り、医学的に小麦を完全に避ける必要はありません。
しかし「小麦が本当に健康的かどうか」を判断する前に、もうひとつ、小麦の歴史と経済的背景を知ることが重要です。
小麦は単なる食品ではなく、国際的な農業政策・貿易・利権と深く結びついてきました。ここでは「輸入小麦の闇」と「日本に小麦が導入された歴史」を整理し、私たちが日常で小麦とどう向き合うべきかを考えます。

輸入小麦の「闇」

ここでは大量に安く輸入される小麦がどのような処理や流通を経ているのか?に焦点を当てています。全ての小麦に当てはまるわけではないですが、多くがそうだ、ということを理解してください。そして、自分や大事な家族がそれを口にしているという事実があること感じてください。
- 農薬使用
栽培期に除草剤や殺菌剤が使われるのは一般的。さらに収穫後には、長期輸送・保管に備えてポストハーベスト農薬や防カビ処理が施されることもある。 - 運搬と保管
輸入小麦は数か月かけて船で輸送され、大型倉庫で長期保管される。カビ毒(マイコトキシン)や害虫対策として薬剤が使われる背景がある。 - 生成処理
精製小麦粉は、保存性・食感を優先するために外皮や胚芽を取り除き、栄養素が削ぎ落とされる。これにより「カロリーはあるがミネラルや食物繊維は乏しい食品」となる。
👉 勘違いしないで欲しいのは、輸入小麦の品質そのものが危険というよりも、流通過程で加えられる処理や栄養価の単純化が問題といえます。
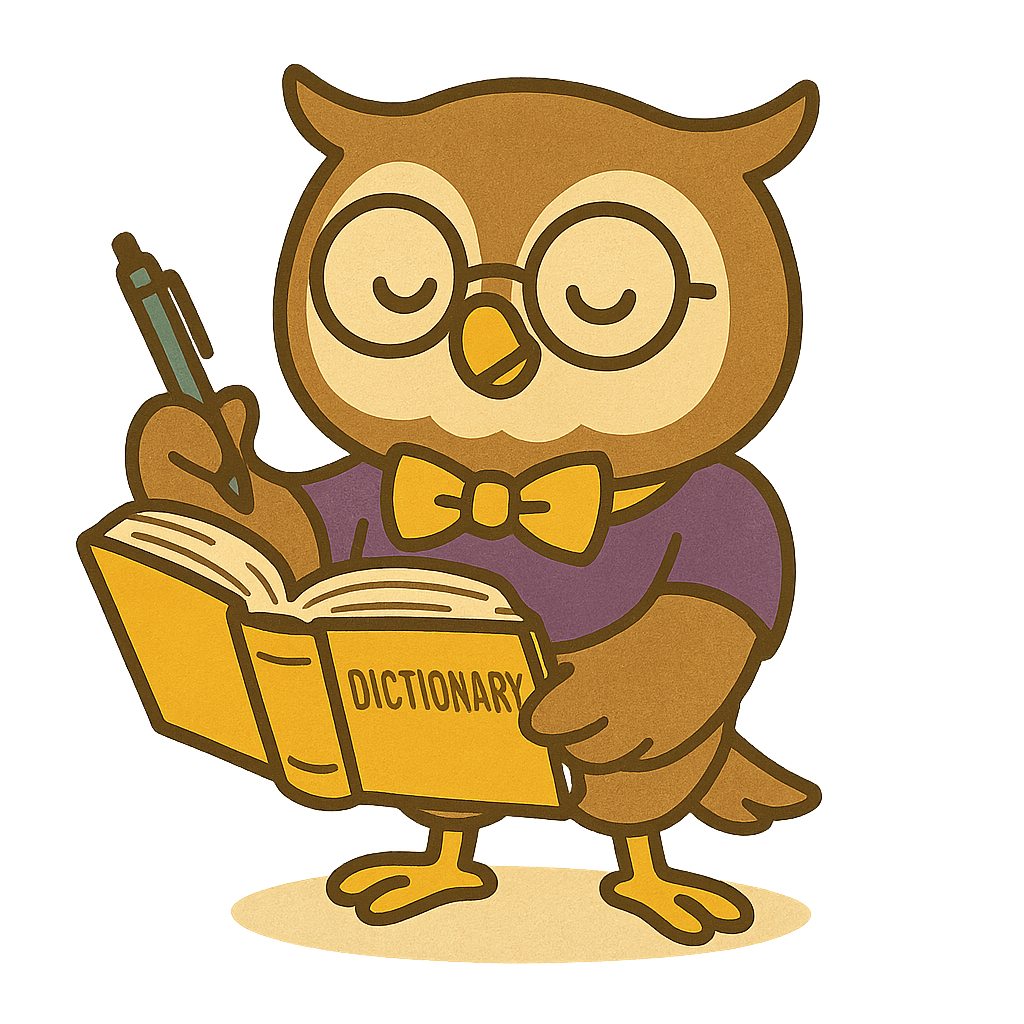
日本に小麦が導入された歴史

もともと日本にはうどんとして小麦文化があるという見方ですが、それも間違っていないと思います。善悪を決めているのではなくて、少なくともこういった歴史的背景がありますよという話です。
- 戦後のアメリカ農業政策
第二次大戦後、アメリカは余剰小麦を処分し、同時に日本の食文化を変えるために小麦を輸出。 - 学校給食への導入
1947年から小麦粉を使ったパン給食が始まり、米から小麦への食文化転換が進められた。栄養改善の名目もあったが、米余りとアメリカの小麦余剰処理が背景。 - 利権構造
食糧管理制度の下、輸入小麦は国が一括買い付け・売り渡しを行い、価格差益(マークアップ)は財源として活用された。現在でも「国家貿易品目」として利権や構造が残っている。
👉 日本人が小麦を「主食的に」消費するようになったのは歴史的にはごく最近であり、自然に選んだというより政策的に押し付けられた面がある。小麦が導入されたここ何十年で日本人の病気が増えているという説もありますが、これらは陰謀論として、あるいは「専門家の意見は必ずしも一致しない」として闇にそれ以上の議論は「意味のないもの」とされてしまいます。

私たちが考えるべきこと

- 小麦は主食の地位を与えられたが、実は日本の気候や農地は稲作向き。小麦の自給率は15%程度にとどまり、依存度は高い。
- 健康上の問題は「グルテン」だけでなく、農薬・精製・貿易構造・食文化の変化と複合的に関わっている。
- すべてを否定するのではなく、「国産小麦を選ぶ」「全粒粉や古代小麦を取り入れる」「代替食品も柔軟に使う」といった 多様な選択肢を持つことが重要。
このような構造を生み出してのは我々人類です。誰が悪いのではなく、消費者として自分を守ための選択をすることが重要です。よく聞くことかもしれませんが、消費者として賢い選択をできるようになることが大事です。
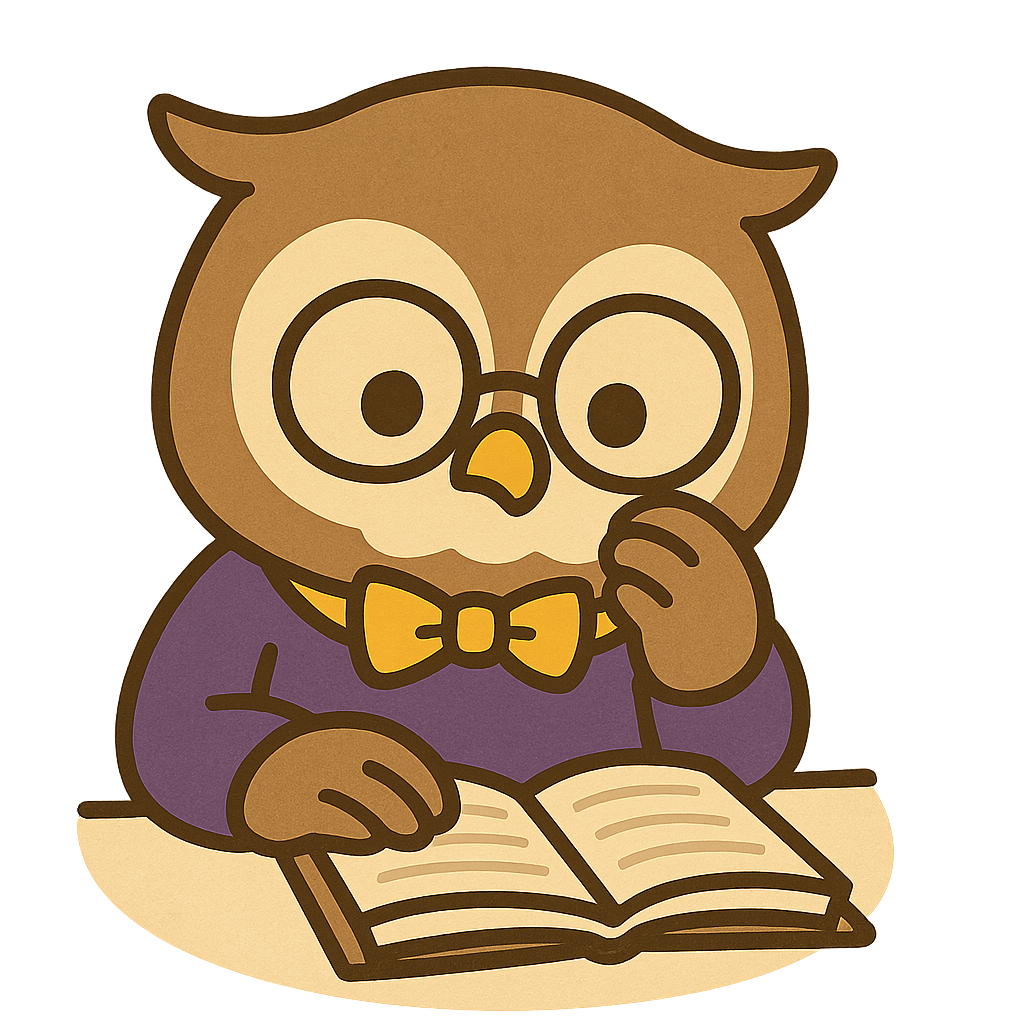
多様な選択肢の例
ひとつは「国産小麦」を選ぶこと。
中でも、自然派食品スーパー(都心だと、こだわりやとかF &Fとか)では少し高いですが「国産小麦」✖️「無添加、無農薬」のような最強の組み合わせ商品に巡り会えます。通常の大手企業の国産小麦よりもグラムあたりの値段は倍くらいしますけど、そこに価値を見出すかどうかは消費者である我々次第ではないかと。
![]() 国産小麦とポストハーベスト農薬に関して
国産小麦とポストハーベスト農薬に関して![]()
「ポストハーベスト農薬(収穫後の防カビ・防虫目的の農薬散布)」は、日本国内では基本的に行われていません。
これは日本の農薬取締法で、収穫後に使える農薬が極めて限られており、食品衛生法で残留基準も厳しく設定されているためです。輸入小麦に関しては、長期船輸送や倉庫保管のリスクがあるため、収穫後に防虫・防カビ処理(例:殺虫剤や防カビ剤)が施されるケースがあります。
→ そのため「ポストハーベスト農薬=輸入小麦に特有」という印象が広まっています。

妻が「パンを作る」というので、国産小麦の強力粉と国産のドライイーストを「こだわりや」で購入。

👆こういったスーパーにあるものよりは値段は倍します。けど、安心感は違いますね。
ふたつ目は全粒粉や古代小麦に注目すること

全粒粉や古代小麦は、現代の精製小麦と比べて栄養面や風味に特徴があります。全粒粉は胚芽や表皮を含むため、食物繊維・ビタミンB群・鉄・マグネシウムなどが豊富で、血糖値の急上昇を抑えやすく、腸内環境改善にも役立ちます。
一方、古代小麦(スペルト小麦、カムット小麦、エインコーンなど)は品種改良が進んでいないため、グルテン含有量や性質が現代小麦とは異なり、消化に優しいと感じる人もいます。また、独特の香ばしさや深い味わいがあり、パンやパスタにするとコクが増すのも魅力です。科学的に「小麦不耐症の人に必ず安全」とは言えませんが、栄養価の高さと食文化的な価値から、健康志向の人に選ばれやすい穀物といえるでしょう。
古代小麦は、楽天とかアマゾンで売っていますが、それ自体を買って調理するというのは少数派だと思います。パンを買ったり、お菓子を選んだりする際に、「知っておく」ことが大事だと思います。
シェフ、サルバトーレクオモ氏が「スペルト小麦」を解説してくれています。
3つ目は代替食品を上手に使うこと

ゼンブパスタは、黄えんどう豆100%で作られたグルテンフリーのパスタ代替食品です。小麦を一切使わずに製造されているため、セリアック病や小麦アレルギーの方でも安心して食べられるのが大きな特徴です。また、豆由来のため食物繊維・たんぱく質が豊富で、血糖値の急上昇を抑えやすい低GI食品としても注目されています。一般的な小麦パスタと比べて噛みごたえがあり、豆特有のコクと香ばしさを感じられるのも魅力。料理のアレンジも幅広く、パスタだけでなくサラダやスープの具材としても活用できます。健康志向や美容、ダイエット中の方にとって、小麦に代わる新しい選択肢のひとつとなりつつある食品です。

ゼンブパスタは時間が経つとややべちゃべちゃになります。熱の管理が大事という印象。スープ系のパスタよりもジェノベーゼやペペロンチーノが合うかなぁと思います。トマトの冷製パスタも合うと思います。

まとめ
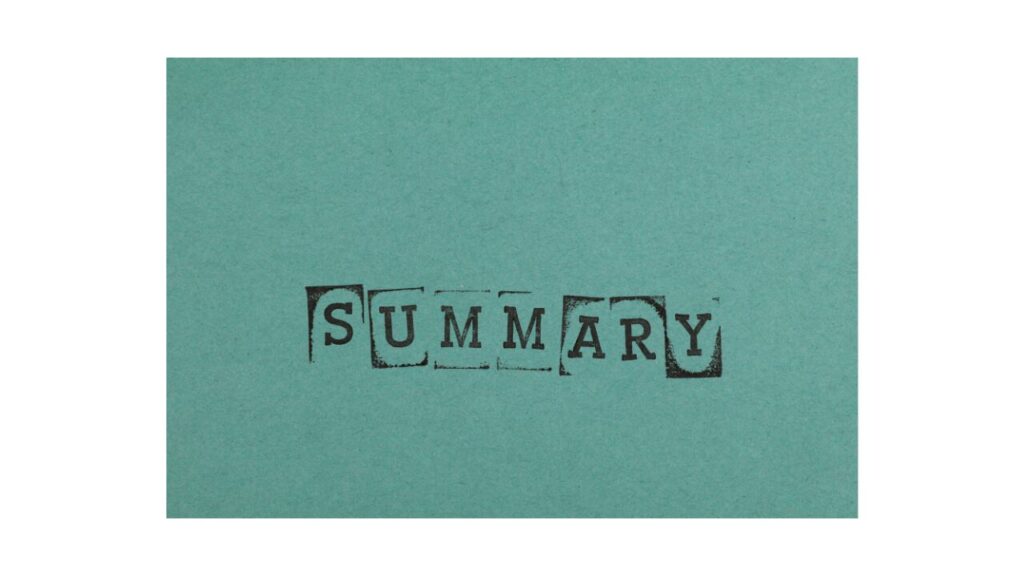
小麦をどう位置づけるかは、単なる栄養学の問題ではなく、歴史・経済・政治の影響を受けていることを理解する必要があります。私たちが日常でできることは、
- 「どこで作られ、どう加工された小麦か」を知ること
- 「食べすぎない・多様な穀物を取り入れる」というバランスを持つこと
です。
健康のためだけでなく、**文化や経済構造を理解したうえで選択することが、現代人にとっての『小麦との向き合い方』**だと言えるでしょう。
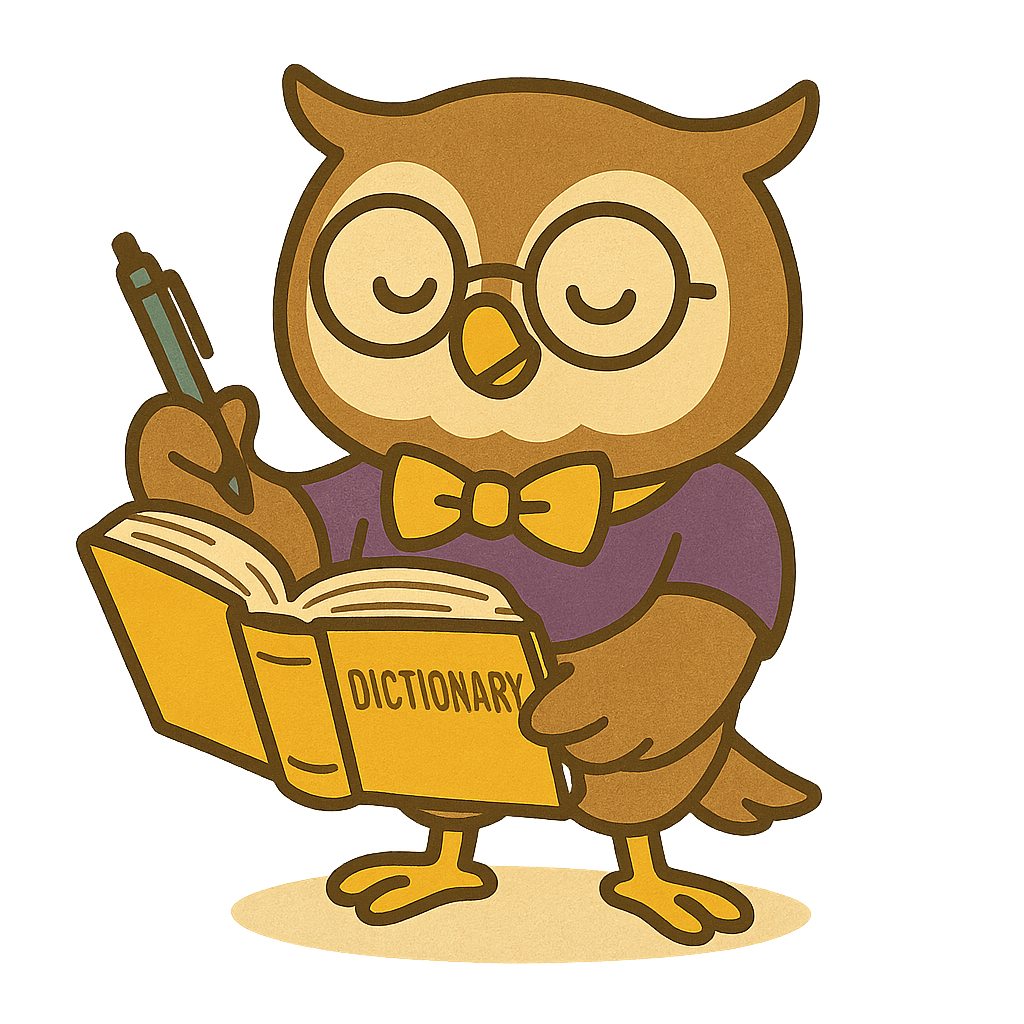

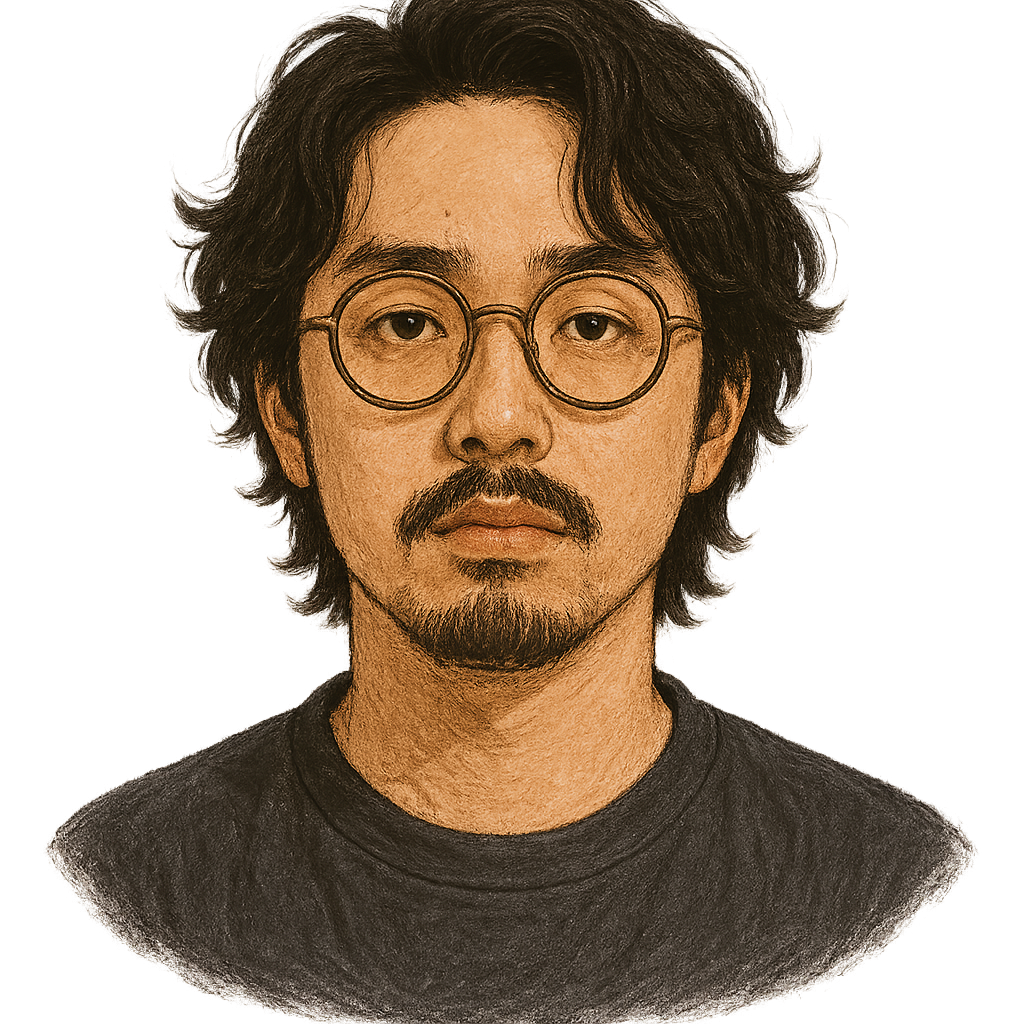


コメント