僕が残していきたい知識のひとつに「アロマセラピー」があります。
これは薬剤師であり、アロマセラピー学会にも所属する僕の母が生涯をかけて学び、実践してきた療法です。
母がアロマを始めた「きっかけ」や「目的」

母としては、僕たち「子供のため」を思って「薬に頼らない治療」を探し求めていたのだと思います。
そして、今度は僕が母の努力を無駄にしないために、「未来の誰かのため」にこの情報を残していきたいと思います。
子供の頃、僕は「過敏性腸症候群」や「アトピー性皮膚炎」に悩まされていました。
他にも「肩こり」など、西洋医学ではうまく対処できない「心身の不調和」は誰にでもあると思います。
漢方などの東洋医学的なアプローチもあります。
僕自身も小学生の時には「過敏性腸症候群」に対して「ミヤBM」という薬と、「ツムラ漢方の99番(小建中湯♨️)」を飲まされていました。
しかし、これがまあ嫌で続きはしません。
お腹が痛い時にたまに飲む、程度になりますよね。
真面目にやればそれで良くなったかも知れません。
ただ、「現実問題として」漢方を飲み続けることのできるお子さんは世の中どれくらいいるんだろうと思います。
そして、たどり着いた方法の一つが「アロマセラピー」であったのだと思います。
「本当に絶好調と言える日は1年にほとんどない」
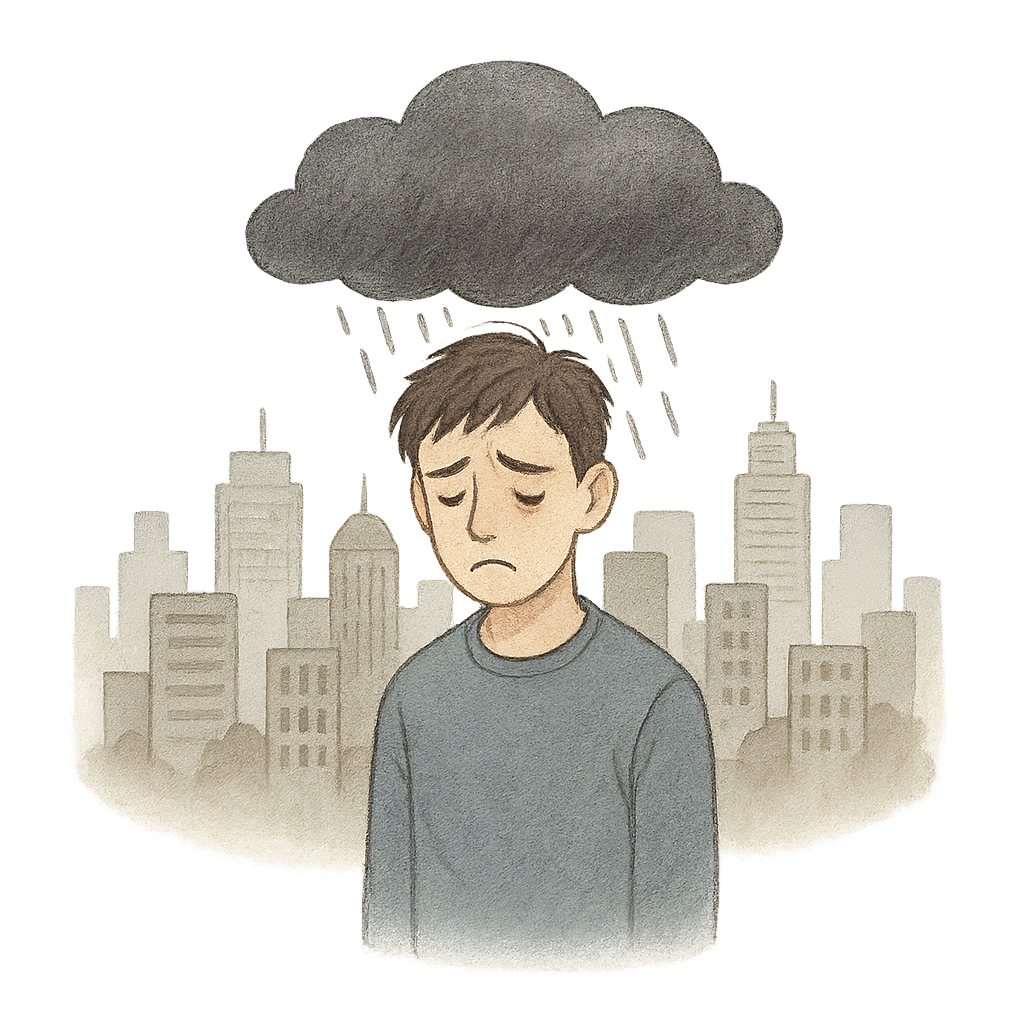
言われてみるとそんな気がしませんか?
僕の母が、そういっていました。
何かしら体は「不調」を訴えてくるのです。
これは内側の問題もあるし、外側の問題もあります。
人間関係であったり、「天気」によるものであったり。
この「不調」を適切に「メンテナンス」しながら「大病」のリスクを減らし
少しでも「絶好調」に近い状態の日々を増やすことが「自分の人生をよく生きる」ために必要だと感じています。
多くの日本人が、子供から大人まで、「ストレス」を抱える日常で、似たような多くの症状に悩まされていると思います。
これに対しては精神や免疫を「整える」ことで症状を和らげたり寛解に近い状態を維持させることが可能です。
西洋医学的アプローチは「整える」「調和をとる」<<「抑える」「停止させる」という性質を持った治療で、「正常な機能」を弱めてしまうことが多くあります。そのため「マッチポンプ」のように、Aという薬の副作用のために、「火消しのために」Bという薬を処方が必要になります。そうして、「おくすり手帳はどんどん分厚くなる」わけです。
医療者として思うこと
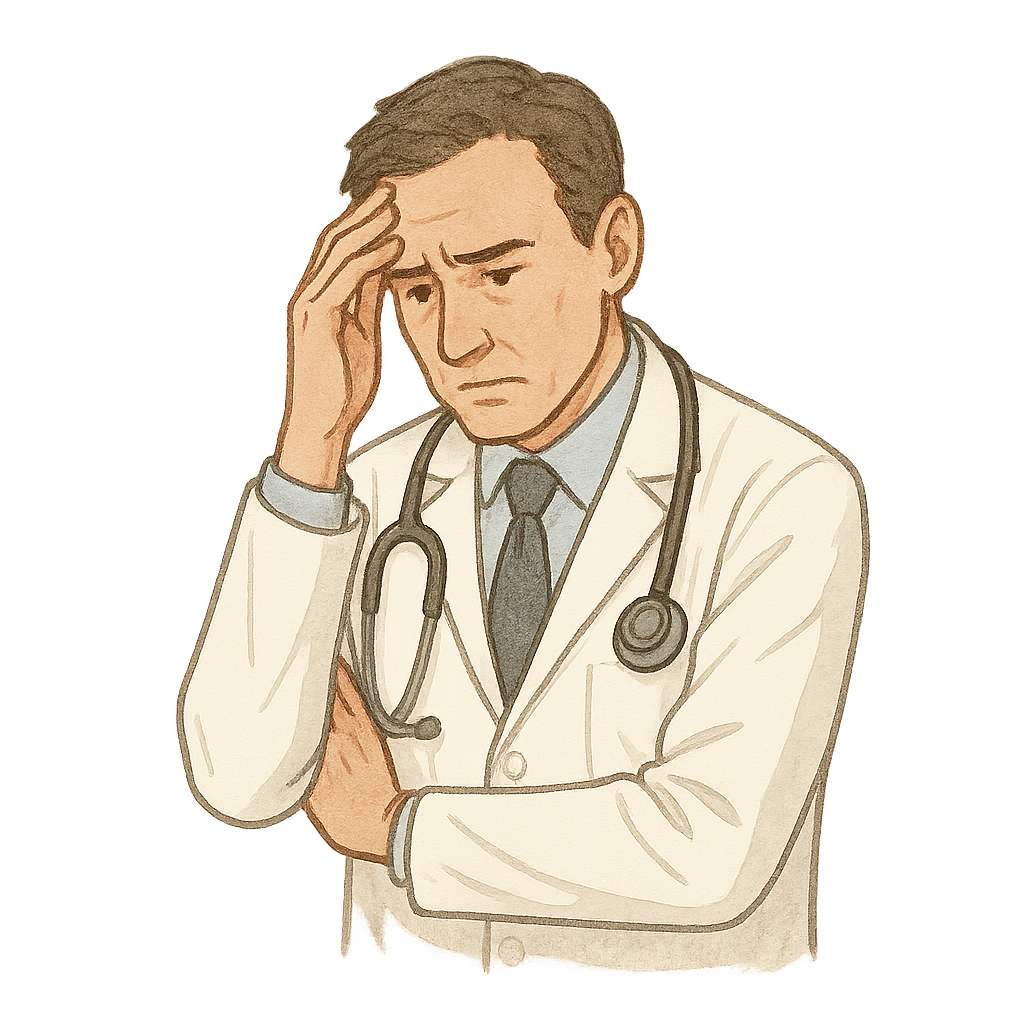
人によっては「人生かけて付き合っていかなければならない症状」があるわけで
これに対して「漫然と薬を使い続ける」ことは、
人生全体を俯瞰してみると「あまり賢い選択ではない」と感じることも多々あります。
もちろん西洋医学を否定しているわけではないです。
西洋医学が優れているのは特に「急性期医療」です。
「整える」余裕がないほどに「急速に破壊」された状態を一刻も早くリカバリーする(脳梗塞、心筋梗塞、外傷など)ためには非常に重要な手段です。
一方で、「体調」を管理する上では、「整える」「調和する」(調整する)ということに焦点を当てた治療法が「選択肢」として現実に(実践可能な状態で)、「身近に」あるべきではないかと感じています。
そのような治療法の1つとして「アロマセラピー」は重要な役割を担っていると思います。
もちろん、「食事」「睡眠」「運動」といった基本的な生活にも十分に注意を払ってください。
ということで、母からアロマセラピーに関して情報をもらい今後少しづつ記事にしていきたいと思います。
まずはアロマセラピーとは何なのか?現代医学における役割を明確にしたいと思います。
記事はこちら👉アロマセラピー入門 アロマセラピーとは???
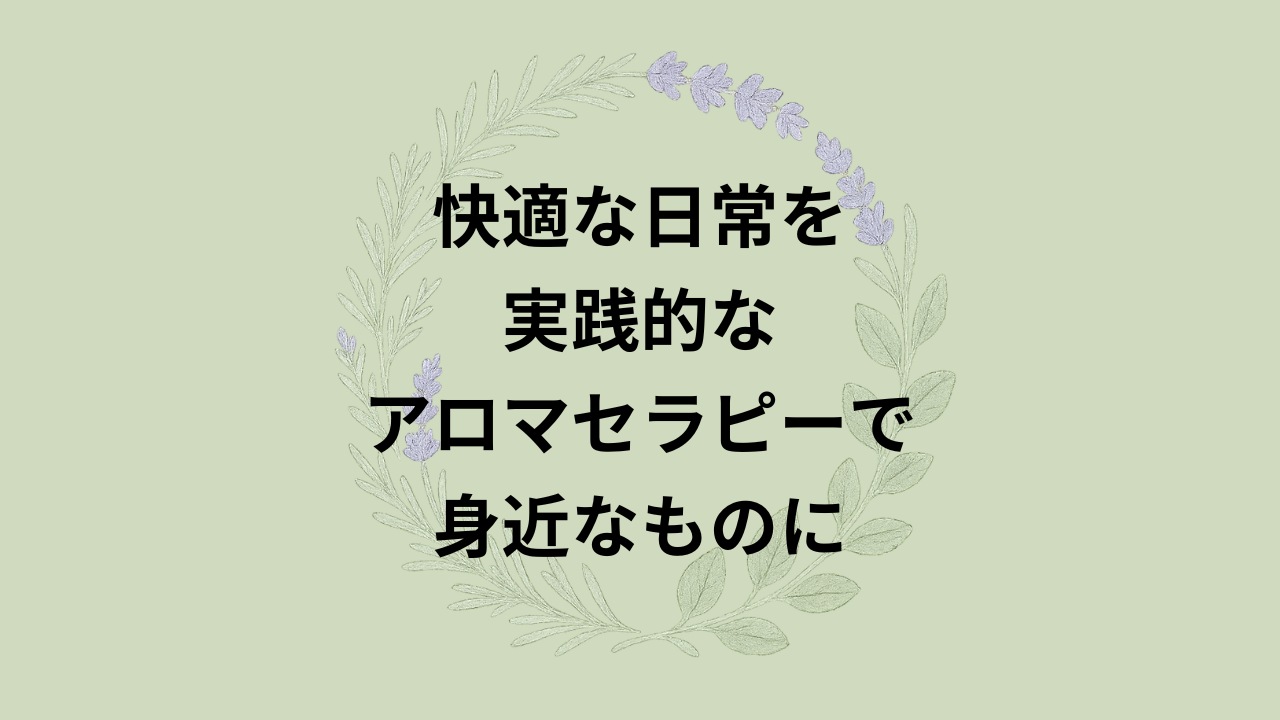
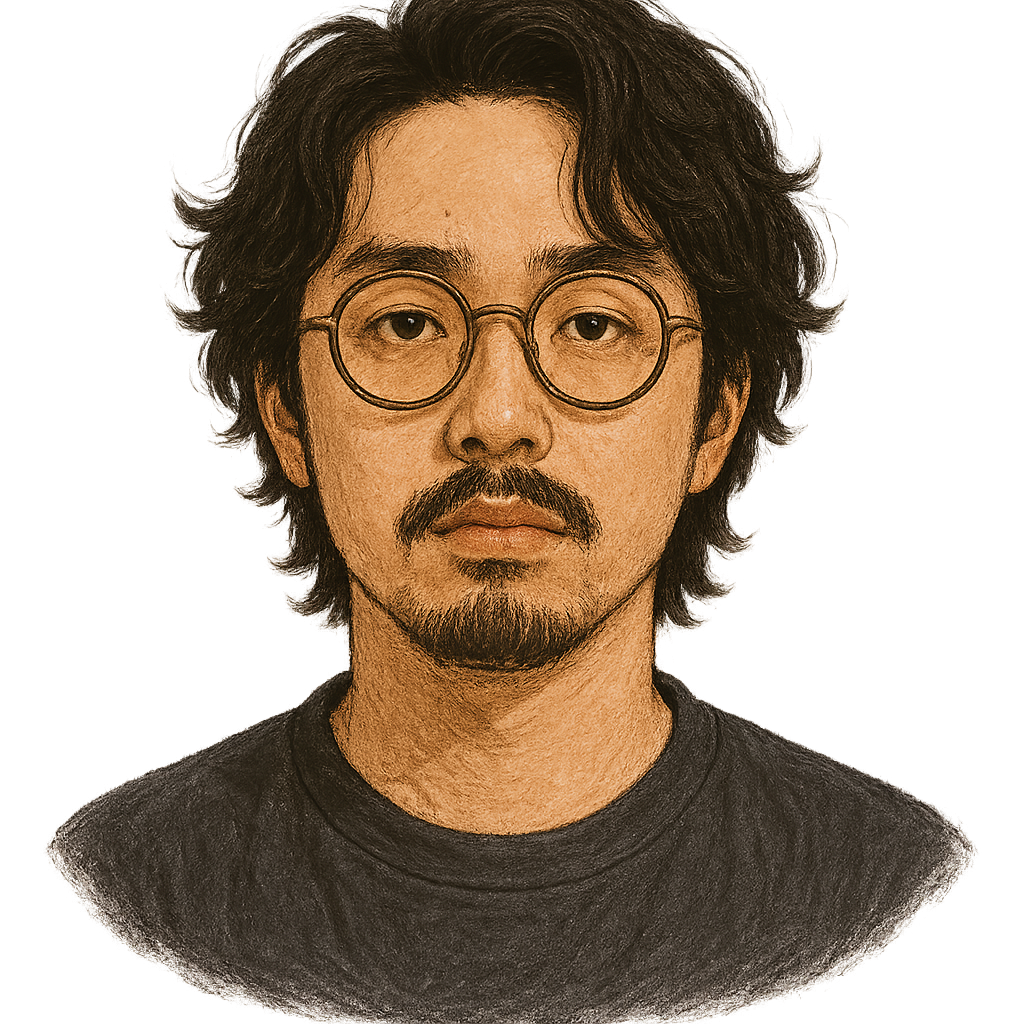

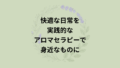
コメント